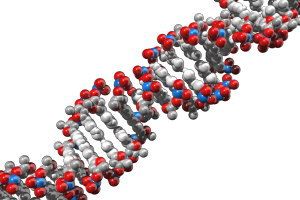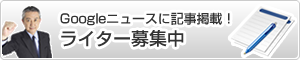- TOP
- >
- 新発見!女と男は違う進化をたどってきた
新着ニュース30件
[PR]
2010年4月19日 23:00
日米の共同チームが発表
性の起源について、従来の説を覆す証拠を日米の共同チームが発見、米科学誌サイエンスで発表した。「生物は雌が基本で、雄は進化の過程で雌が変化して生まれた」とする説が従来の説。今回の発見は、雌雄の区別のできる最も原始的な生物の遺伝子から、すでに雄と雌それぞれに特有の遺伝子が発見されたというものだ。つまり、雄は雄、雌は雌として別々に進化の道をたどってきたというのだ。
侠(おとこぎ)遺伝子と緋牡丹(ひぼたん)遺伝子
4年前の研究で野崎久義・東京大学准教授らは、緑藻「ボルボックス」の雄株から、精子に似たたんぱく質を作る雄特有の遺伝子、侠(おとこぎ)を発見。この時、雌株からは雄雌共通の遺伝子しか見つからなかったため「雌が基本でそこに新しい機能が加わって雄になった」という従来の説が正しいと考えられた。しかし、今回の研究において、雌雄両方の遺伝子情報をすべて解読した結果、雌にしか存在しない5個の遺伝子を発見。野崎准教授はこれを緋牡丹(ひぼたん)遺伝子群と命名。また、新たに雄にだけ存在する遺伝子9個を発見した。
原始的な生物において雌雄それぞれの遺伝子が発見されたことについて、教授は「性の起源までさかのぼると、雄雌は根本的に違う進化をたどったことがわかる」と話している。
緋牡丹(ひぼたん)は富司純子の映画から命名
緋牡丹という名は野崎准教授が大ファンだという富司純子の映画「緋牡丹博徒」からつけられた。教授にとっても、まるで背中に彫られた緋牡丹のように衝撃的な発見だったのだろう。ちなみに侠(おとこぎ)遺伝子も、野崎准教授の好きな任侠映画からの命名だ。このあたり、准教授の個性が垣間見える。分かり合えそうで分かり合えない、男と女。今回の発見はもしかするとケンカ中のカップルにとっては新発見どころか周知の事実だったかも知れない。
オス特異的遺伝子“OTOKOGI”の発見
[PR]
-->
記事検索
ユニーク特集

株式会社ファーストキャビン

変態企業カメレオン

株式会社エイタロウソフト

株式会社GABA

株式会社リクルートエージェント
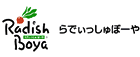
らでぃっしゅぼーや株式会社

株式会社ツナグ・ソリューションズ

株式会社ネビュラプロジェクト

使えるねっと株式会社

株式会社ECC
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ
モバイルサイトQRコード
チェッカーズ!モバイルサイトへアクセス
htt