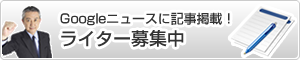- TOP
- >
- 宝の持ち腐れか?最先端のレスキューロボット
新着ニュース30件
[PR]
2011年3月20日 22:00
待機中のレスキューロボット
放射能汚染が懸念される福島第1原子力発電所。文部科学省の要請に基づいて「原子力安全技術センター」から仙台に送りこまれた、遠隔操作で放射能測定のできる「防災モニタリングロボット」は、いまだに宮城県県庁で待機中である。原発内に、操作できるスタッフが入れないからだ。NPO法人「国際レスキューシステム研究機構(IRS)」のメンバーが用意した、生存者探索用ヘビ型ロボット「能動スコープカメラ」(東北大・田所教授)や、被災地を自由自在に走る自走式ロボット「クインス」(千葉工業大・小柳未来ロボット技術研究センター副所長)も出番を待っているが、お呼びが来ない。
「阪神大震災」(平成7年)以来、日本の災害救助ロボットの開発は飛躍的に進歩した。しかし、今回の大震災では生かす手立てはない。被災地の行政には、ロボットに対応する余裕がないからだ。
IRS副会長の松野京都大教授はレスキューロボットを活用する上で、今回、行政側にも研究者側にも大きな課題が残ったとしている。
原子力安全技術センター
国際レスキューシステム研究機構
[PR]
-->
記事検索
ユニーク特集

株式会社ファーストキャビン

変態企業カメレオン

株式会社エイタロウソフト

株式会社GABA

株式会社リクルートエージェント
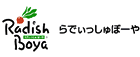
らでぃっしゅぼーや株式会社

株式会社ツナグ・ソリューションズ

株式会社ネビュラプロジェクト

使えるねっと株式会社

株式会社ECC
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ
モバイルサイトQRコード
チェッカーズ!モバイルサイトへアクセス
htt